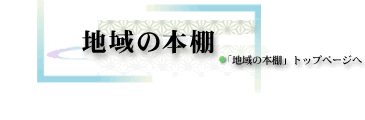
入力に使用した資料
底本の書名 昔、こんな人が 郷土の先人「THE かがわ」
底本の編者 香川県
底本の発行者 香川県
底本の発行日 平成17年6月〜平成22年10月(通巻664号〜通巻728号)
入力者名 香川県立図書館
校正者名 香川県立図書館
入力に関する注記
文字コードにない文字は『大漢和辞典』(諸橋轍次著 大修館書店刊)の
文字番号を付した。
登録日 2008年1月29日
1 「長谷川佐太郎(はせがわさたろう)(1827〜1898年)−私財を投じて満濃池を修築」(2005年6月号)
2 「三土忠造(みつちちゅうぞう)(1871〜1949年)−香川県初の大臣は努力の人」(2005年7月号)
3 「壷井栄(つぼいさかえ)(1899〜1967年)−人間とふるさとを愛し続けた作家」(2005年8月号)
4 「大西権兵衛(おおにしごんべえ)(生年不詳〜1750年)−命をかけた農民一揆」(2005年9月号)
5 「岡内清太(おかうちせいた)(1863〜1944年)−香川の教育の大恩人」(2005年10月号)
6 「塩飽諸島の人々−35人もが咸臨丸に乗船」(2005年11月号)
7 「菊池寛(きくちかん)(1888〜1948年)−学生時代のマント事件」(2005年12月号)
8 「真念(しんねん)(江戸時代 生没年不詳)−四国遍路の父」(2006年1月号)
9 「西嶋八兵衛(にしじまはちべえ)(1596〜1680)、
平田与一左衛門(ひらたよいちざえもん)(1602〜1656)、
矢延平六(やのべへいろく)(生年不詳〜1685年)−ため池をめぐる人々」(2006年2月号)
10 「津島寿一(つしまじゅいち)(1888〜1967年)−戦後日本の賠償交渉」(2006年3月号)
11 「小村田之助(おもれたのすけ)(1624〜1644年)−農民のために命を捨てた若き庄屋」(2006年4月号)
12 「南原繁(なんばらしげる)(1899〜1974年)−戦後初の東大総長」(2006年5月号)
13 「大久保韑之丞」(おおくぼじんのじょう)(1849〜1891年)−四国新道建設に人生をかけた」(2006年6月号)
14 「保井コノ(やすいこの)(1880〜1971年)−日本初の女性理学博士)(2006年7月号)
15 「山崎宗鑑(やまざきそうかん)(1465?〜1553年ごろ)−香川に住んだ俳諧の祖」(2006年8月号)
16 「大松博文(だいまつひろふみ)(1921〜1978年)−東洋の魔女を育てた監督」(2006年9月号)
17 「笠置シヅ子(かさぎしづこ)(1914〜1985年)−日本の復興へ力を与えた歌手」(2006年10月号)
18 「池田勇八(いけだゆうはち)(1886〜1963年)−動物を愛した彫刻家」(2006年11月号)
19 「柴野栗山(しばのりつざん)(1736〜1807年)−世直しに力を尽くした儒学者」(2006年12月号)
20 「宗道臣(そうどうしん)(1911〜1980)−少林寺拳法の創始者」(2007年1月号)
21 「大浦留市(おおうらとめいち)(1896〜1989年)−初めてオリンピックに参加した選手」(2007年2月号)
22 「鬼無甚三郎(きなしじんざぶろう)(1834〜1907年)−松盆栽を香川に根付かせた」(2007年3月号)
23 「久米栄左衛門通賢(くめえいざえもんみちかた)(1780〜1841年)−マルチな才能をもった塩田開発の父」
(2007年4月号)
24 「松平頼重(まつだいらよりしげ)(1622〜1696年)−水不足から民を救った初代高松藩主」(2007年5月号)
25 「有馬忠三郎(ありまちゅうざぶろう)(1879〜1958年)−弁護士の地位向上に努めた先覚者」(2007年6月号)
26 「水原茂(みずはらしげる)(1909〜1982年)、三原脩(みはらおさむ)(1911〜1984年)
−野球王国・香川を築いたライバル」(2007年7月号)
27 「軒原庄蔵(のきはらしょうぞう)(1828〜1890年)−難工事の末に弥勒石穴を完成」(2007年8月号)
28 「二宮忠八(にのみやちゅうはち)(1866〜1936年)−世界初の飛行器模型を香川で開発」(2007年9月号)
29 「藤川勇蔵(ふじかわゆうぞう)(1883〜1935年)−ロダンに学び近代彫刻の精神を伝える」(2007年10月号)
30 「三原スエ(みはらすえ)(1903〜1986年)−恵まれない少女800人の母となった」(2007年11月号)
31 「中村恭安(なかむらきょうあん)(1833〜1883年)−地域医療に貢献したほうそうの神様」(2007年12月号)
32 「両児舜礼(ふたごしゅんれい)(1853〜1891年)、棚次辰吉(たなつぐたつきち)(1874〜1958年)
−手袋王国・東かがわの始祖」(2008年1月号)
33 「井上通女(いのうえつうじょ)(1660〜1738年)−女博士とたたえられた女流文学者」(2008年2月号)
34 「野網和三郎(のあみわさぶろう)(1908〜1969年)−世界で初めてハマチの養殖に成功」(2008年3月号)
35 「小西和(こにしかなう)(1873〜1947年)−瀬戸内海国立公園の生みの親」(2008年4月号)
36 「三木茂(みきしげる)(1901〜1974年)−メタセコイヤを発見した植物学者」(2008年5月号)
37 「今雪真一(いまゆきしんいち)(1892〜1967年)−県民の海外移住を支えた『南米移民の父』」(2008年6月号)
38 「加地茂治郎(かじもじろう)(1869〜1940年)−豊稔池を造り、農民を干ばつから救う」(2008年7月号)
39 「瀬山四郎兵衛(せやましろべえ)(1784〜1853年)−藩の財政難を救った丸亀うちわの功労者」(2008年8月号)
40 「宮井茂九郎(みやいもくろう)(1853〜1906年)−“桃源郷のまち”を生んだ、桃栽培の先覚者」(2008年9月号)
41 「植田平太郎(うえだへいたろう)(1877〜1949年)−剣道一筋に生きた〝昭和の剣聖〟」(2008年10月号)
42 「納富介次郎(のうとみかいじろう)(1844〜1918年)−高松工芸高を創立し工芸文化の基礎を築く」(2008年11月号)
43 「向山周慶(さきやましゅうけい)(1746〜1819年)−白砂糖作りを確立し讃岐の特産品とする」(2008年12月号)
44 「花岡タネ(はなおかたね)(1878〜1967年)−明治時代に女性教育の先駆けとなる」(2009年1月号)
45 「藤川三渓(ふじかわさんけい)(1816〜1889年)−水産・軍事で日本の近代化に貢献」(2009年2月号)
46 「井上甚太郎(いのうえじんたろう)(1845〜1905年)−香川の塩業を守り、産業振興に力を注ぐ」(2009年3月号)
47 「中山城山(なかやまじょうざん)(1763〜1837年)−今も読みつがれる郷土史書の作者」(2009年4月号)
48 「片岡弓八(かたおかゆみはち)(1884〜1958年)−難事業を成し遂げた世界に誇る潜水王」(2009年5月号)
49 「高丸伊平(たかまるいへい)(1864〜1951年)−愛林思想を育てた郷土の名士」(2009年6月号)
50 「遊佐正憲(ゆさまさのり)(1915〜1975年)−県人初の金メダリスト」(2009年7月号)
51 「太田伊左衛門典徳(おおたいざえもんてんとく)(?〜1707年)−肥土山村の治水事業に成功」(2009年8月号)
52 「新田藤太郎(にったとうたろう)(1888〜1980年)−戦後香川の芸術を育てた彫刻家」(2009年9月号)
53 「椎名六郎(しいなろくろう) (1896〜1976年)−日本の図書館学の先駆け」(2009年10月号)
54 「末澤喜市(すえざわきいち) (1864〜1931年)−錦松盆栽の元祖」(2009年11月号)
55 「後藤芝山(ごとうしざん) (1721〜1782)−讃岐の学校教育の始祖」(2009年12月号)
56 「河田迪斎(かわたてきさい)(1805〜1859)−幕末の日米交渉に尽力」(2010年1月号)
(#「迪」は旧字)
57 「山田兼松(やまだかねまつ)(1903〜1977)−塩田から世界へ駆けた鉄人」(2010年2月号)
58 「真木信夫(さなぎのぶお)(1892〜1974)−「塩飽魂」を守り続けた郷土史家」(2010年3月号)
59 「木村黙老(きむらもくろう)(1774〜1856)−藩政を支え文化を愛した名家老」(2010年4月号)
60 「真嶋正市(まじままさいち)(1886〜1974)−日本の応用物理学の父」(2010年5月号)
61 「藤村トヨ(ふじむらとよ)(1876〜1955)−体育教育にささげた生涯」(2010年6月号)
62 「脇太一(わきたいち)(1900〜1969)−才気あふれる作詞家」(2010年7月号)
63 「猪熊弦一郎(いのくまげんいちろう)(1902〜1993)−好奇心と向上心に満ちた画家」(2010年8月号)
64 「杉田秀夫(すぎたひでお)(1931〜1993)−誠意を尽くし瀬戸大橋を架ける」(2010年9月号)
65 「景山甚右衛門(かげやまじんえもん)(1855〜1937)−郷土の近代化を進めた実業家」(2010年10月号)