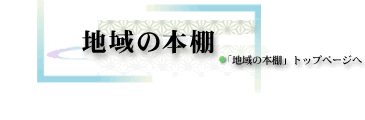
入力に使用した資料
底本の書名 香川県史 別編2 年 表
底本の編集 香川県
底本の発行 香川県
底本の出版 四国新聞社
底本の発行日 平成三年三月二十日
入力者名 渡辺浩三
校正者名 渡辺美智子
入力に関する注記
・文字コードにない文字は『大漢和辞典』(諸橋轍次著 大修館書店刊)の
文字番号を付した。
・JISコード第1・2水準にない旧字は新字におきかえて(#「□」は旧字)
と表記した。
登録日 2005年5月17日
考 古 年 表 −2− 前 期 旧 石 器 時 代 200万年前 オルドヴァイ猿人文化形成される(チョッパー,チョッピングトウール等の礫器と 削器等の小型剥片石器が知られる)東アフリカ・タンザニア湖畔の遺跡FLKI地点 では猿人(オーストラロピラクス,ボイセイ)頭骨1個体分,両生類,爬虫類,鳥 類,小型哺乳類(齧歯網,幼年豚,レイヨウ)の破砕骨が伴う. 170万年前 元謀猿人文化形成される(中国雲南省,石英岩製のスクレイパー,原始ノロジカ, カリコテリウム,最後枝角鹿,サーベルタイガーなどの第三紀残存種に,リサン, ハイエナ,雲南ウマ,山西アキシスジカの前期更新世種が伴う.花粉分析から亜熱 帯の草原森林環境であったことが知らされる) アフリカ,ヨーロッパ,ユーラシア東部に原人が生息する. 100万年前 アシュール原人文化形成される(猿人文化にハンド・アクスニ両面加工石核石器) が加わる.前期,後期に二分され,後期では骨角製木製の棒状ハンマー(ソフトハ ンマー)による優れた剥離技術が認められる.東アフリカ・タンザニアの湖畔の遺 跡BK2地点では巨大ヒヒ,サイ,キリン,カバなどの大型動物,カモシカ多種, ハイエナなどの肉食動物,齧歯網の小動物,オーストリッチの卵殻,ワニ等の爬虫 類の破砕骨が伴う. この文化に至ってヒトは大型獣の集団猟が可能となる. 大型獣の分配組織として,一夫一婦を核とする経済単位が形成されるか―,家族の 確立. アフリカ,ヨーロッパ,ユーラシア東,南部に原人が生息する.ジャワ原人(イン ドネシア)生息する. 藍田原人文化形成される(中国陜西省―チョッパー,チョッピングトウール等の礫 器とスクレイパー,使用痕のある剥片等が知られる.周辺で出土したジャイアント パンダ,トウヨウゾウ,オオバク,中国バクから,温暖で若干湿潤な森林草原が復 原される) 70万年〜20万年前 北京原人周口店文化形式される(中国北京市―周口店第1地点の文化層1〜13層 は,1〜7層=晩期,8〜13層=早期の2期に区分される.基本的石器組成はスク レイパーを主体とし,尖頭器,チョッパー,チョッピングトウール,彫刻刀で,晩 期に尖頭器,彫刻刀が増加,石錐,エンドスクレイパーが出現する.早,晩期通じ て直接打法,両極打法が盛行するが,次第に改良される.花粉分析から今日の華北 とほぼ同じか,やや温暖湿潤な気候であったとされる―周口店間氷期) 宮城県・中峯C遺跡7層(熱ルミネッセンス年代測定法―36万8300±2万4700 年前,小型剥片石器類,大型の礫器出土.両極打法が知られる等,周口店第1地点 に類似する) 中峯C遺跡6層(熱ルミネッセンス年代測定法―14万±6200年 −3− 前,フィッショントラック年代測定法−21万1000年前) 馬場壇A遺跡20層(フィッショントラック年代測定法―13万年前以前) 日本列島におけるミンデル氷期以降の中部更新世の動物群に,楊子虎,ヒョウ,ヒ グマ,周口店サイに近い種が知られるが,これは華北の周口店動物群に類似する. 氷期の寒冷気候による動物,そして北京原人の列島への移住があったか. 中 期 旧 石 器 時 代 10万年前 旧人,シベリアに進出する(北緯55°) 愛知県・牛川人骨,旧人に属する. 埋葬を行うようになる(屈曲姿勢が多い.イラクのシャニダール洞穴では男性,小 児各1体の埋葬人骨を花びらが覆う) 周口店第15地点遺跡が形成される(中国北京市・ルヴァロワ剥片,小型両面加工 尖頭器,スクレイパー,尖頭器,石錐,彫器,礫器,石球等が知られる) イゲチェイスキー・ロク1遺跡が形成される(ソ連邦アンガラ流域,縦長剥片,ム ステリアン尖頭器,ラウンドスクレイパー,小型両面加工石器などが知られる) 馬場壇A遺跡19層上面,10層上面,中峯C遺跡4層上面,座敷乱木15層上面の 石器群が形成される(これらの遺跡群の変遷から,チョッピングトゥール,ピック, 両面加工の石斧類から,各種スクレイパー,鋸歯縁石器等の加工が進んだ小型剥片 石器へと変化する.スクレイパーの一種=斜軸尖頭器,円盤状石核に特徴がある. 石器の形は幾分整うが,以後のものと比較して不定形である.周口店第15地点石 器群と類似する) 東京・多摩No.471―B遺跡(両極打法,小型尖頭器)が知られる. 後 期 旧 石 器 時 代 4万年前 新人出現.新大陸に居住地を拡大する. 三ケ月人・浜北人(静岡)港川人(沖縄) 3万年前(中国) 劉家岔(中国甘粛省)・富裕河(中国山西省)遺跡が形成される(中国後期旧石器 文化第1期―石刄技法が出現) 水洞溝遺鉢(中国回族自治区)が形成される(中国後期旧石器文化第2a期―石刄 技法・ナイフ形石器) 2万5000年前 峙峪遺跡(中国山西省,中国後期旧石器文化第2b期―ナイフ形石器,細石刄技法 の出現) 1万5000年前 襄汾柴寺遺跡(山西省),小南海遺跡(河南省)形成される(中国後期旧石器文化 第2c期―ナイフ形石器,細石刄技法卓越) 1万年前 虎頭梁遺跡(河北省),周口店山頂洞遺跡(北京市)が形成される(中国後期旧石 器文化第3期―発達細石刄) 2万5000年前 ウスチノフカ1遺跡(ソ連邦沿海州)が形成される(日本・茂呂型ナイフ形石器に 酷似するナイフがある.他に幌加型細石刄 −4− 核,掻器,彫器,石錐,ノミ状石器,荒屋型彫器,片刄石斧,両面加工尖頭器,剥 片尖頭器が知られる) (極東アジア) スヤンゲ遺跡4(韓国)が形成される(剥片尖頭器,両面石器,チョッパー,削器, 掻器,ナイフ形石器,角錐状石器、荒屋型などの彫器,石刄,石刄核,クサビ形細 石刄核,スキー状ポールが知られる) 2万5000年〜1万年前 クサビ形細石刄核が揚子江以北〜シベリア極北圏,西シベリア〜モンゴル,朝鮮半 島,日本列島,カムチャツカ半島,アラスカ半島,アリューシャン列島に広がる. 荒屋型彫器がバイカル湖周辺,モンゴル東部,中国東北部,沿海州,極東,朝鮮半 島,日本列島,アリューシャン列島,アラスカ半島に広がる. 3万年〜1万4000年前(日本) 関東地方で5期に区分できる旧石器文化が知られる.1期ナイフ状石器,揉錐器, 削器,礫器,2期茂呂型,切出形ナイフ形石器を主体に削器,掻器.彫器,石刄, 局部磨製石斧,敲石.末期に蛤良火山灰層が形成,3期2期石器群に尖頭器様石器 が加わる.4期尖頭器様石器は改良槍先形尖頭器に.6期槍先形尖頭器が主体,7 期細石刄,削器,円錐形細石刄核,船底形細石刄核出現. 2万1000年前 鹿児島湾奥部姶良火山が爆発し,火山灰(AT)が東北地方に迄及ぶ.ヴュルム氷 期中極寒期に位置する(−7℃)―海水面が現在より約100メートル下がったため (海退)間宮海峡,宗谷海峡が陸つづきとなる.朝鮮海峡,津軽海峡は冬期に結氷 し,アイスブリッジがかかるか. 広島大学キャンパス(広島県東広島市)に平地住居からなる集落が形成される. 大阪府堺市南花田遺跡に不整円形の堅穴住居が形成される. 中国山地ではAT層真上から国府型ナイフ形石器が出土する. 環瀬戸内地方に国府型ナイフ形石器が分布する―瀬戸内2期旧石器文化,(香川県 最古の旧石器型式)瀬戸内海は草原が広がり,湖沼が発達する. 国分台,金山のサヌカイトが中,四国地方に搬出される. 九州地方に九州型ナイフ形石器が分布する(剥片尖頭器を伴う). 東北地方に杉久保型ナイフ形石器が分布する. 環瀬戸内地方のナイフ形石器製作技法で並列剥離法が主体となる―瀬戸内2期旧石 器文化. 1万4000年前 細石刄文化が広がる―瀬戸内3期旧石器文化(九州,東日本に船底形〈クサビ形〉 細石刄核の密な分布があり,近畿,中国,四国,関東に円錐,角錐形の細石刄核の 密な分布が知られる.彫器,削器,掻器が伴う) −5− 原 縄 文 時 代 1万3000年前 土器の発明(堅果類,肉の煮沸) 弓矢の発明(狩猟)釣針の発明(漁撈) 尖頭器の改良―有舌尖頭器の出現(狩猟) 石皿,磨石の増加(堅果類の調理)局部磨製石斧の増加(木器の製作)磨製石斧の 出現. 細石匁,木葉形尖頭器等旧石器文化要素の消滅. 温暖化進む(−5℃)このとろ,最終氷期が終わり,完新世が始まる.列島の寒冷 気侯に適応し,草原を食料源にしたナウマン象,オオツノジカ等が絶滅し,森林の 堅果類,芽等を食料源とした中小哺乳類―ニホンシカ,イノシシ,ツキノワグマ, キツネ,タヌキ,ノウサギ,ニホンザルが増加する.亜寒帯針葉樹林が減少し,広 葉樹林,照葉樹林が広がる.氷河が溶け世界的に海水面が上昇する(海進) 大池(高松市)羽佐島(坂出市与島町)国分台(綾歌郡国分寺町)兎子山(綾歌郡 国分寺町)で有舌尖頭器出土.土器を出す遺跡は未検出.旧石器文化と比較して凋 落ぶりがはなはだしい. 中,四国の土器を出土する遺跡に不動ケ岩屋(隆起線文,多縄文土器―高知県)上 黒岩(隆起線文,無文土器―愛媛県)馬渡岩陰(無文土器―広島県)遺跡がある. 他期に比較して洞穴,岩陰の居住利用が顕著である.このころ,列島の夏季多雨, 冬期多雪の気侯の原型が形成されつつある.岩陰,洞穴居住の主因か. 大麻栽培される(福井県鳥浜貝塚). 縄 文 時 代 早 期 1万年前 縄文時代始まる(縄文文化―後氷期第1期文化) 貝塚の形成か盛んになる(神奈川県夏島貝塚等) 土偶出現する. 8000年前 このころ海進が緩慢になる. 礼田崎貝塚(小豆郡土庄町)大浦(坂出市櫃石島)小蔦島貝塚(三豊郡仁尾町)備 中地遺跡(仲多度郡琴南町)等が形成される.黄島式押型文土器,蔦島式無文土器 が知られる.小蔦島貝塚はハマグリ,アサリ,ハイガイ等,岩礁に隣接する泥海底 産が占める.しかし,礼田崎貝塚は半鹹半淡のヤマトシジミが殆んどを占め,周辺 の海化がなお不十分であったことが知られる.遺跡分布の中心が島嶼部で,住居地 は山丘(島)の尾根上にあり,旧石器時代の生活立地が踏襲される. 7000年前 このころ海進が強まる. 6300年前 鹿児島県鬼界カルデラが大爆発し,火山灰(アカホヤ)が九州中南部,四国,山陽, 紀伊半島と,広範囲に降下堆積する.当該期の繊維土器は,瀬戸内一帯では希薄. 環境激変により, −6− 瀬戸内早期人は他地域に流出したか. 縄 文 時 代 前 期 6000年前 前期初頭の土器型式,羽島下層1式は,土庄町豊島神子ケ浜遺跡,坂出市櫃石島大 浦浜遺跡等,県域の東部,北部域で出土し,西部,南部では出土しない―前期文化 は,東あるいは北から始まり,後半に至って西部,南部に拡大された. 荘内半島は,まだ無住の地である. このころ,島嶼浜堤砂州上に居住地を移す(大浦浜遺跡,坂出市ナカンダ浜遺跡な ど)高松平野,阿讃山脈山麓台地(下司遺跡)三豊平野,阿讃山脈山麓末端沿岸台 地(南草木貝塚)にも居住する.縄文時代生活立地4類型の内,3類型が出る.地 域の中心集落である長命型遺跡の多くは前期に出現する.―香川県縄文社会の確立 期. 5500年前ころ 海進がクライマックスに達する. 東日本で環状住居配置の集落が増加する. 堅果類の貯蔵穴が作られる. エゴマ(鳥浜貝塚,長野県荒神山)ゴボウ,リョクトウ,ヒョウタン(鳥浜貝塚) が栽培される. 縄 文 時 代 中 期 5000年前 荘内半島に縄文人が進出する.三豊平野の遺跡は,南草木遺跡を残して途絶える. 海退が進む.寒冷化. 中部山岳地帯(八ヶ岳西南麓,天龍川水系)関東西部では文化の興隆をみる.狩猟 は低調だが,植物性食料への依存が深まり,さらに焼畑農耕が実施されるか.(中 期農耕論) エゴマ(パン状炭化物の主成分.長野県大石・曽利・上前尾・月見松・岐阜県ツル ネ遺跡)が栽培される. 有〔キ〕式(♯「キ」は文字番号40897)(かえりを持つ)釣針の開発がすすむ. 回転式離頭銛が北海道から東北地方太平洋沿岸部に広がる.網錘(礫石錘を除く) が,関東から東西に分布を拡大―漁撈技術の進展と漁業体制の確立. 中期末 中部山岳地帯の文化が衰退する―海退を引き起こす寒冷化が影響したか. 東海地方西部,近畿地方土器諸型式,瀬戸内里木2,3式に関東地方土器型式加曽 利E式の影響が認められる. 縄 文 時 代 後 期 4000年前 前 半 各地で文化・社会の再編成が進む. 瀬戸内一帯で遺跡数が激増(中期後半と比較して,香川県では2〜3倍)寒冷化の 累積的な影響で,植相が複雑化―堅果類の増加,海退の拡大による干潟の拡大―貝 類をはじめとする水産資源の増加によって得られた食料事情の好転が内的発展を促 し,長命型親村(地域の中心集落)から多数の子村が形成された.東に称名寺式, 西に中津式の近似した土器型式が成立する. 関東,東海と近畿,中,四国間の交流の盛行を示すか. −7− 関東地方では後期に至って狩猟の比重が増加する.多量の土偶,石棒,石剣の出土 は,これらが狩猟祭儀に用いられたことを示すか. 後 半 太平洋沿岸部において,大型,極大型の結合式釣針が開発される.仙台湾で燕形回 転離頭銛が開発される.―外洋性漁業が高度に発達.内湾性漁具にヤスが加えられ る.霞ケ浦一帯で土器製塩が始まる.―地域の風土に対応した漁業の進展(適応の 深化が,この時期の縄文文化の傾向である.) 関東地方では大型集落が激減し,環状の住居配置も不明瞭になる. 東北地方では大型の墓地が形成される(秋田県・大湯環状列石等). ヒョウタン(千葉県多古田,福岡県四箇遺跡)ソバ(千葉県苗見作,福井県浜島, 宮崎県平畑遺跡)エゴマ(東京なすな原遺跡)が栽培される. 県域の沖積低地,河川流域に遺跡が形成される(善通寺市永井,観音寺市樋の口遺 跡など)永井遺跡では後期後半から晩期前半の当地域の土器型式に,関東後期半ば の加曽利B式注口土器が共伴する. 多量のドングリ,土器,カゴ,石皿,磨石,打製石斧(土掘り具)サイドスクレイ パー(ナイフ)その立地から植物性食糧への傾斜が一段と深まったことを知らせる. ヒョウタン出土.樋の口遺跡は財田川下流左岸の自然堤防上に立地.後期半ばの土 器彦崎KI式に北九州鍾ケ崎式土器が伴出.石包丁状石器出土. 西日本縄文文化の変革期−このころ,中,四国,九州に新しい石器,生活立地が出 現.愛媛県岩谷遺跡では後期後葉に打製石斧が初現,松山市船ケ谷,大渕と後期後 半の沖積低地への進出が認められる.岡山県では後期末迄に打製石斧,石包丁状石 器が出現.又沖積低地,山間低地,海浜部に立地拡大される.九州では後期半ばに 打製石斧初現,後葉に石包丁状石器初現.後期後葉から晩期前半にかけて,阿蘇山 麓の火山灰台地で集落が大発展―イネ,オオムギ出土(晩期農耕説)熊本県の沿岸 部で貝塚が大型化する. 注口土器,土偶,石棒等,東日本縄文文化要素が西日本に一般化する. 縄 文 時 代 晩 期 3000年前 前 半 県域島嶼部の遺跡で後期末から晩期前半に中断する長命型集落が多い.(坂出市ナ カンダ浜,土庄町伊喜末遺跡等)沖積低地へ進出か. 後 半 西日本突帯文土器分布圏に大陸水稲農耕文化の伝播(第1次)大陸系磨製石器(石 包丁,大形蛤刄石斧.扁平片刄石斧,柱状 −8− 抉入片刄石斧)木製農耕具(両手鍬,広鍬,馬鍬,えぶり)鉄器(北九州,長行遺 跡―性格不明)等の弥生時代主要生産用具が,このころ既に伝播する.福岡・板付, 佐賀・菜畑遺跡では水田,堰址,岡山・江道遺跡では水田址,兵庫・丁田,口酒井, 大阪・長原遺跡では籾あるいは籾痕,大阪・牟礼遺跡では堰址が検出されている. 高松市林坊城遺跡で木製農具(鍬等)出土. 島嶼部の集落が再開(坂出市・ナカンダ浜,土庄町伊喜末遺跡等)沖積低地に新し い集落(林坊城遺跡など)が生まれ,弥生時代前期に続く.大陸水稲農耕文化の伝 播のルート,定着に関連した縄文社会の改編が進む. ソバ(宮崎・平畑,千葉・加曽利,埼玉・真福寺,青森・石亀,亀ケ岡,岩手・丸 年橋,北海道・尻島東風泊)ゴボウ(北海道・江別太)等が主に東日本,亀ケ岡式 土器分布圏で栽培される. 縄文時代終末に至って西の突帯文土器分布圏の大陸水稲農耕に対し,東の亀ケ岡式 土器分布圏の東アジア北方農耕が対峙する. 弥 生 時 代 前 期 前 半 大陸水稲農耕文化の伝播続く(第2次−福岡県板付遺跡の2重環濠,同朝倉郡東小 田峰遺跡の墳丘墓)東方へは日本海沿岸,瀬戸内沿岸,太平洋沿岸沿いの3コース が知られるが,この時期すでに点的に東北地方まで波及する(秋田県地蔵田遺跡に 棚囲いの集落―移住者の集落か.) 県域にも岡山・塩飽諸島を通じて沿岸部に伝播(櫃石島大浦浜遺跡―坂出市下川津, 観音寺市室本遺跡)続いて三豊,丸亀,高松各平野の沖積低地徴高上に水稲農耕村 落が形成される(善通寺市稲木,高松市天満遺跡等) 後 半 前期後半に至って集落拡散,数も激増する(観音寺市・一の谷―竪穴住居,樋の口, 長砂古.善通寺市・五条,三井,永井,旧練兵場.綾歌町・行末,次見.丸亀市・ 中の池―環濠集落.坂出市・鴨,高松市・光専寺山―環濠集落か.三木町・香川大 学農学部,大内町・落合遺跡等) 近畿地方で方形周溝墓つくられる(大阪府池上遺跡) BC221 秦始皇帝中国を統一. 朝鮮半島から銅剣,矛,戈等の青銅器伝播. 近畿地方で銅鐸の製造が始まり(菱環鈕式)同地方に流通する. 近畿地方環濠集落始まる(京都府扇谷遺跡) 弥 生 時 代 中 期 BC220〜BC150 中期初頭の佐賀県宇木汲田遺跡の12号甕棺に細形銅剣,多鈕細文鏡が副葬される. BC202 劉邦,前漢を建てる. 初 期 沖積低地の開発進む(高松市サコ・長池遺跡)善通寺市・旧練 −9− 兵場遺跡継続され,同彼宗遺跡が始まる. 沖積低地の前期集落の多くが廃絶される. 前 半 瀬戸内沿岸部山丘高所に集落が設けられる(高地性遺跡―詫間町・紫雲出山,北谷 遺跡.岡山県貝殻山遺跡) 岡山を中心に,西端北九州,東端大阪湾沿岸,南端高知,北端島根の範囲に分銅形 土製品広まる. 近畿地方で外縁付鈕式銅鐸が製造される.近畿地方を中心に島根,広島,香川を西 界,愛知を東界として流通する. このころ,東日本に水稲農耕文化が普及,定着する. BC108 前漢武帝,朝鮮半島に楽浪,玄莵,臨屯,真番郡を置く.南鮮にも馬韓,辰韓,弁 辰の三韓併立. このころ,倭人は百余国に分かれ,その一部は楽浪郡と交渉を持つ(漢書地理志) 福岡市吉武高木遺跡に特定集団墓.中心の3号木棺墓には銅剣2,銅矛,銅戈各1, 多鈕細文鏡1,勾玉1,管玉100が副葬され,特定集団中の特定個人墓の出現が認 められる. 大阪市爪生堂遺跡2号方形周溝墓に,特定家族の形成が認められる. 後 半 このころ,県域に周溝墓伝わる(高松市サコ・長池遺跡). 中国地方に墳丘墓出現(岡山県四辻遺跡)大型器台供献される.県域の平野周辺の 山丘に集落が営まれる(高松市・久米池南,中山田遺跡等) 善通寺市矢ノ塚遺跡,掘立柱建物が建設される.日常用土器に伴ってミニチュア土 器,鳥形土製品,銅剣形土製品,分銅形土製品出土. BC1C 前 半 北部九州で立岩式(3期後半)の甕棺に多量の前漢鏡―中国洛陽焼溝漢墓副葬鏡2 期―前漢宜帝(BC74〜BC49)〜元帝(BC49〜BC33)が副葬される(福岡県三 雲南小路1号―王墓か,2号甕棺,同須玖岡本,同立岩堀田10号甕棺) 北部九州で青銅製銅剣,銅矛,銅戈の国産化進む.祭器として発展する.横帯文銅 鐸,北部九州で製造される(福岡市赤穂浦,佐賀県安永田遺跡)島根,鳥取,岡山, 広島県下の邪視文を持つ等,特徴的な福田型の分布は,その流通の東界を示すか. 扁平鈕式銅鐸が近畿地方で製作され,中,四国,近畿,東海を流通圏とする.県域 銅鐸の大部分はこれに属する. 中細型銅剣が中,四国に普及し,近畿地方を中心とした銅鐸分布圏,北部九州を中 心とした銅矛分布圏・横帯文銅鐸分布圏の三種の青銅祭器分布圏が中部瀬戸内地方 で交錯する. 4式土器に地域相互の交流盛ん―土器絵画(高松市・久米池南遺跡の高床建物線刻 壷) −10− 島根県東部で銅剣358,銅矛16,銅鐸6が保有される(島根県荒神谷遺跡) 近畿地方で大規模な方形周溝墓が築かれる(大阪市加美遺跡,南北22メートル, 東西11メートル,盛土高1.9メートル)高松市久米池南高地性遺跡で銅剣を副葬 した土〔コウ〕墓(#「コウ」は文字番号なし)がつくられる−族長墓か. AD8 王〔モウ〕(#「モウ」は文字番号なし)が中国に「新」を建てる. AD25 後漢開始(漢の復興) 北部九州で桜馬場式(4期)の甕棺に後漢初期の平縁方格規矩鏡(焼溝漢墓3期後 半)が副葬される. 愛知県朝日環濠集落遺跡で逆茂木・忍びがえし(バリケード)を備える.関東に環 濠集落が増加. 瀬戸内沿岸部で土器製塩始まる. 弥 生 時 代 後 期 中部瀬戸内海沿岸部で高地性遺跡廃絶される.土器の交流途絶える 高松市上天神遺跡,竪穴住居2棟,掘立柱建物10数棟建設される.打製石包丁, 銅鏃出土. 近畿地方後期初頭の土器に貨泉(「新」の貨幣―AD25―40鋳造)伴出する.岡山 県高塚遺跡で上東式(後期前半)に貨泉伴出.同遺跡で突線鈕式銅鐸埋納坑に上東 式包含. AD57 倭の奴国王が後漢に朝貢して光武帝から印綬を受ける(後漢書東夷伝)―福岡県志 賀島で金印として出土. 山陰地方で四隅空出型墳丘墓出現. 近畿,東海地方で空線鈕式銅鐸つくられる.岡山,徳島,高知東半を西界とし,東 海地方まで流通する. 前 半 北部九州で広形銅矛つくられる.愛媛,高知を東界とする. 平形銅剣が瀬戸内沿岸部に流通する. 西日本では銅矛,銅剣,銅鐸の3流通圏が鼎立する. AD107 倭国王師升,後漢に入貢. 鉄製農,工具普及する. 後 半 県域沖積低地の集落が再開,あるいは新村の形成で集落数が激増. 後漢もしくは〔ホウ〕製(♯「ホウ」は文字番号00420)(倭製)の破鏡が普及(善 通寺市・彼の宗,稲木遺跡など). このころ,倭国大いに乱れ,攻伐続く. 山口,愛媛,近畿地方の瀬戸内東西界で高地性集落が再び盛んになる. 岡山地方墳丘墓に大型特殊壷,器台の供献が定着する. 卑弥呼期 県域で積石墓(善通寺市稲木遺跡)箱式石棺墓(善通寺市仙遊遺跡―石棺石材に鯨 面〈いれずみ〉を表現した顔等が線刻される―愛知県亀塚遺跡の壷形土器,岡山県 一倉遺跡の鉢形土器の −11− 線刻画に同一の様式を認めることができる)小規模な竪穴式石室墓(綾歌町石塚山 古墳群等―前方後円形の墳丘墓を含む)など,様々な墓がつくられる. 岡山県楯築墳丘墓築造される(双方中円形,埴輪の原形となる特殊器台・壷形土器 が供献される) 220〜222 倭の諸国,邪馬台国の卑弥呼を共立し女王となす(魏志倭人伝) 後漢滅び,魏・呉・蜀の三国時代始まる. 239 卑弥呼,大夫難升米らを魏都洛陽に送る.明帝,卑弥呼を親魏倭王として金印紫綬 を与える.加えて五尺刀2口,銅鏡100枚等を与える. 〜248 卑弥呼死去.大いに冢をつくる.男王に服さず相誅殺する. 卑弥呼の宗女壹與を立て,国中安定する(魏志倭人伝) 265 魏滅び西晋おこる. 266 倭の女王壹與,西晋に貢献する(晋書武帝紀) 奈良県纏向遺跡,各地の土器集まる.近畿庄内式土器,各地に流通. 青銅製祭器が廃棄される(寒川町森広遺跡では細かく破砕された扁平鈕式銅鐸が集 落外縁部に捨てられる) 坂出市下川津遺跡,弥生時代末から古墳時代前期に至る集落建設される.竪穴住居 36棟,水田,板状鉄斧,小型〔ホウ〕製鏡(♯「ホウ」は文字番号00420)出土. 三角縁神獣鏡が近畿政権によって各地の首長に配布される. 高松市鶴尾神社4号墳築造される.香川,岡山,兵庫西部の中東部瀬戸内沿岸部で 前方後円形の墳丘墓が築造され,前方後円墳の祖型となる. 古 墳 時 代 前 期 前 半 奈良箸墓,京都椿井大塚山古墳等,定形化された前方後円墳が近畿地方に成立し, 地方に及ぶ(定形化し発達した2段の前方部,3段の後円部,長大な竪穴式石室と 割竹形木棺,埴輪の樹立,三角縁神獣鏡を中心とする中国鏡,鉄刀,剣,鏃,銅鏃, 革綴短甲,冑,鉄製農工具,硬玉製勾玉,碧玉製管玉,青色系ガラス小玉等の副葬) ―全国首長霊祭祀を前方後円墳祭祀に整備統一し,近畿地方を核とした三角縁神獣 鏡配布体制をより高次の政治的ネットワークに発展させる. 準構造船築造される(大阪府八尾市・久宝寺遺跡) 県域各地に前方後円墳が築造される(寒川町奥3号墳―盛土墳,高松市石清尾山古 墳群―積石塚,善通寺市野田院古墳―前方部盛土,後円部積石,等) 後 半 割竹形石棺がつくられ,前方後円墳の埋葬施設に用いられる(中期前葉まで続く, 綾歌町快天山古墳―鷲の山産,津田町赤山古墳―火山産等)大阪柏原市安福寺の石 棺,鷲の山産の石でつくられる. 沿岸部の古墳築造が盛んになる(岩崎山4号墳等津田古墳群, −12− 高松市・長崎鼻古墳,横立山経塚,坂出市・ハカリゴーロ古墳,田尾茶臼山古墳等 宇多津古墳群,黒藤山4号墳等多度津古墳群) 三豊平野北部に観音寺市・鹿隈カンス塚築造される(円墳) 前方後円墳が九州中部から東北地方南部まで広がる. 福岡県沖ノ島で海上祭祀始まる. 391 倭国軍,渡海して百済,新羅軍を破る(高句麗.広開土王碑) 古 墳 時 代 中 期 直島町荒神島で海上祭祀始まる(〜8世紀). 朝鮮半島から北部九州に横穴式石室伝わる. 大王墳(近畿王権)奈良盆地北部から大阪平野南部に移り,巨大化する(古市古墳 群―伝応神天皇陵等.百舌古墳群―伝仁徳天皇陵等)長持形石棺用いられる. 421 倭王讃,宋に朝貢する(宋書倭国伝)以後,6世紀初頭まで,倭の五王(讃・珍・ 済・興・武)歴代宋に遣使,安東将軍倭国王の称号授かる. 石清尾山古墳群,石船塚築造.以後,造墓絶える.一方,香東川対岸に今岡古墳築 造される(日本唯一の空心磚陶棺を前方部に埋納する)高松平野最大の三谷石船塚, 築造されるが,以後,南部で前方後円墳の築造絶える. 各地で最大級の前方後円墳の築造始まる(岡山・造山古墳等) 前 半 大川町で四国最大の前方後円墳,富田茶臼山古墳築造される.以後,東讃では前方 後円墳の築造絶える. このころまでに,朝鮮半島南半部から穴窯を用いた製陶法伝わり,大阪・陶邑を中 心に各地に須恵器の生産が始まる(初期須恵器窯―福岡,朝倉窯,香川,高松,三 谷三郎池窯,高瀬,宮山窯など) U字形鋤,鍬先,大形曲刄鎌,馬鍬等,朝鮮半島から伝播,鉄製農耕具革新される. 近畿政権,鉄器製産・供給の一元化を進める―大阪府墓山古墳・陪塚野中古墳,応 神陵古墳の陪塚・アリ山古墳等に多量の鉄製武器,農具,工具類が埋納. 後 半 大阪・陶邑,須恵器の定型化(倭風化)をすすめ,地方に配給するなど,全国須恵 器生産の核となる. 鋲留衝角付冑,三角板鋲留短甲,眉庇付冑,挂甲,馬具が副葬される―乗馬が普及. 千葉県稲荷台1号墳副葬の鉄剣に「王賜」の銘がある. 県域各地で,鉄製武器・武具(甲冑)・馬具・農工具・須恵器を非常に地域色豊か な竪穴系石室,箱式石棺に副葬する中,小円墳の群集墳が形成される(6世紀前半 まで.寒川町・石井七つ塚,長尾町・川上古墳,綾南町・岡御堂古墳群,津頭古墳 群, −13− 綾上町・末則古墳群,満濃町・公文山古墳等) 沿岸,島嶼部で箱式石棺を埋葬施設にした方墳などが築造される(坂出市沙弥島・ 4人塚,香川郡・荒神島,葛島(♯「葛」は旧字),高松市・女木島,丸山古墳― 金製垂飾付耳環副葬)以降,丸亀平野東部以東では前方後円墳の築造絶える. 観音寺市・丸山古墳(円墳),青塚古墳(前方後円墳)の石棺に阿蘇石が用いられ る(九州との交流) このころ,各地で豪族居館の諸型式が出現する(大阪府・大園遺跡,群馬県三ツ寺 1遺跡). 難波津に大倉庫群建設される(大阪府・難波宮下層遺跡)畿内政権に属するか. 紀ノ川下流域に大倉庫群建設される(和歌山県・鳴滝遺跡)大豪族に属するか. 471(辛亥年) 埼玉県稲荷山古墳副葬の鉄剣に「辛亥年」「杖刀人」 「〔ワ〕加多支〔ル〕大王」(#「ワ」「ル」文字番号なし)の銘がある. 熊本県江田船山古墳副葬の鉄剣に「典曹人」の銘がある(他の副葬品―金銅製帯金 具・冠帽・沓・金製垂飾付耳飾等,豪華で国際色に富む―金銀の装身具) 478 倭王武,宋に上表し,安東大将軍倭王となる. 古 墳 時 代 後 期 527 横穴式石室普及. 近江毛野臣,任那復興のため出発.筑紫国造磐井が新羅と通じて反乱を起こし,毛 野臣を阻む(書紀) 528 物部麁鹿火,磐井を斬殺―福岡県岩戸山古墳はその墓か. 製塩活動盛行(製塩集団の祭祀―船形土製品・ミニチュア土器,坂出市櫃石島・大 浦浜遺跡) 前 半 須恵器生産盛行(志度町・末1号窯,丸亀市・青の山窯など) 善通寺市・王墓山古墳築造される(香川最後の前方後円墳?,最古の横穴式石室墳, 金銅製冠帽,花形文様銀象嵌の鉄刀,馬具などの副葬,石屋形・埴輪―北部九州と の交流顕著) 観音寺・母神山古墳群開始(瓢箪塚《♯「箪」は旧字》―40メートルの前方後円 墳,鑵子塚―円墳30メートル以上,單鳳環頭,把頭の大刀など副葬―を首長墓と する4群50基) 538 百済の聖明王,仏像と経論を献じる―仏教公伝(元興寺縁起) 後 半 県域各地に横穴式石室をもつ群集墳の形成が広まる(首長層は巨石を用いた横穴式 石室を築造―大野原町・椀貸塚,平塚,角塚.坂出市・綾織塚.高松市・古宮権現 社大塚,久本古墳.寒川町・中尾古墳等) 島根県岡田山1号墳出土の鉄刀に「額田部臣」の銘がある. 善通寺市・宮ケ尾古墳をはじめ,大麻山麓,坂出市五色台西麓の横穴式石室に線刻 壁画が施される. −14− 坂出市下川津遺跡,竈を作りつけた竪穴住居,掘立柱建物が建設される.大型掘立 柱建物地区から圭頭太刀把頭,碧玉製管玉,金銅製耳環,勾玉出土. 585 物部守屋,仏法破却を奏上.天皇これを認める.守屋,塔,仏殿を焼き,仏像を難 波江に捨てる(書紀) 敏達天皇没する.敏達陵は天皇陵最後の前方後円墳.以降,天皇陵は方墳を基本と する. 587 蘇我馬子ら,守屋を滅ぼす. 588 蘇我氏法興寺(飛鳥寺)建立. 593 聖徳太子摂政となる. 603 冠位十二階を制定する. 604 憲法十七条を制定する. 607 小野妹子を隋に派遣する. 各地で群集墳の築造続く.奈良県上之宮遺跡で,最古の庭園が建設される. 630 第1回遣唐使を派遣する. 645 中大兄皇子,中臣鎌足ら,蘇我入鹿を暗殺する. 初めて年号を立て,大化とする. 646 改新の詔を宣布する. 649〜664 「大花下」(冠位)記載の木簡が用いられる(飛鳥京跡出土―「白髪部五十戸」記 載の木簡伴出. 横穴式石室に追葬続く. 660 唐,新羅連合軍により百済滅ぶ. 斉明天皇,百済救援のため難波宮に移る. 663 日本,百済軍が唐,新羅軍に敗れる(白村江の戦い) 667 近江大津宮に遷都. 九州から瀬戸内沿岸,畿内に山城築造される(大和国・高安城,讃岐国・屋嶋城, 城山,吉備国・鬼ノ山,伊予国・永納山,太宰府・大野城など) 坂出市下川津遺跡,7世紀から10世紀に至る集落建設される. 墨書土器,緑釉陶器,越州窯青磁椀,石帯,円面硯,土馬,陶馬,木製の鞍橋,鐙, 独楽,琴柱,犂等出土.木製品は7世紀に属する.出土遺物,掘立柱建物の一部に 官衙的要素を持つ. 県域各地に,有力氏族による寺院建立盛ん(綾氏・飯山町法勲寺,佐伯氏・前善通 寺など) 670 戸籍をつくる(庚午年籍) 672 壬申の乱. 699 「己亥年十月上挾國阿波評松里」記載の木簡用いられる(藤原京跡出土) (己亥年=文武3) 奈 良 時 代 700ころ 坂出市櫃石島タテハ・ヤケヤマ山麓で国家的海上祭祀行われ −15− る.善通寺市稲木遺跡B地区,掘立柱建物群建設される. 観音寺市柞田八丁遺跡隣接地で陶印(須恵質「封印」)出土. 讃岐国分寺・国分尼寺建立―山内瓦窯操業,国分寺に瓦供給. 800〜900 善通寺市中村遺跡で,溝中から銅印(私印「貞」)と銅製帯金具巡方出土―溝はN ―30°―Wの方向をとる. このころ,人形(ひとがた)を用いたお祓が広まる(善通寺市下所遺跡) このころ,水田開発盛ん(高松市サコ・長池遺跡,同サコ,松ノ木遺跡,坂出市・ 下川津遺跡)このころの高松平野の農地開発を伝えるものに天平7年(735)12月25 日弘福寺領讃岐国山田郡田図がある. 奈良中ころ,綾南町陶邑古窯群が讃岐における須恵器生産を独占するようになる. 平 安 時 代 綾南町陶邑古窯群で瓦を生産するようになる. 胞衣(えな)埋納習俗広まる(善通寺市稲木遺跡C地区の屋敷地で埋納土師器甕 に収納.承和昌宝(835年初鋳が伴出) 10世紀 このころ,琴南町・中寺廃寺跡が営まれる. このころ,讃岐国調として陶〔ボン〕(♯「ボン」は文字番号21452)12口・有柄 大〔●〕(#読み不明・文字番号なし)12口・小筥杯2,000口など18種3,151個の 須恵器が課せられている(延喜式) 11世紀末ころ 西村遺跡1号窯を含む綾南町・陶邑古窯群で,京都鳥羽離宮南殿屋瓦が焼かれる. 12世紀 このころを中心として,綾南町・西村遺跡(窯業集落か)が営まれる. このころの柱穴跡,溝跡,遺物等が坂出市・讃岐国府跡で検出される. 12世紀末ころ このころ,坂出市下川津遺跡で,岡山・早島式土器(土師質)畿内産瓦器(楠葉型 等)が用いられる―畿内の寺社領的性格を示すか. このころから13世紀初めに,坂出市・大浦浜遺跡で粘土土坑を利用した製塩活動 が行われるが,短期で終わる.その後,漁業が盛んとなる. 鎌 倉 時 代 13世紀 このころ,陶邑古窯群で須恵器の生産が終了する.以後,14世紀まで瓦質碗の小 規模な生産が行われる. このころ,豊中町・延命遺跡が営まれる. このころから14世紀まで,高瀬町・矢ノ岡遺跡(掘立柱建物17棟,溝状遺構,井 戸出土.軸線はN―30°―Wをとる)が営まれる. このころから14世紀中葉ころまでに,利生寺遺跡(室町時代の竪穴住居?出土) が営まれる. このころ,坂出市下川津遺跡で,綾南町・西村遺跡(陶邑古窯 −16− 群の一部)で生産された瓦質土器が盛んに用いられる. 14世紀 このころ,豊浜町・大木塚遺跡が営まれる. このころ,坂出市・大浦浜遺跡の石組遺構(護岸施設か)が営まれる. 室 町 時 代 14世紀中葉 香西氏天霧城築く このころを中心として,高瀬町・大門遺跡(掘立柱建物,礎石建物,土〔コウ〕(#「コウ」は文字番号なし),石組み 井戸,石組溝状遺構,瓦質土器,備前焼,青磁,鉄鋤先,銅銭出土)が営まれる. 14世紀後半 このころから15世紀初めに,国分寺町・国分寺楠井遺跡で,土師質土器の土釜・ 土鍋,瓦質土器のすり鉢・こね鉢等が焼かれる. 14世紀末ころ このころ,大内町・水主神社所蔵大般若経函が製作される. 15世紀 このころ,仲南町・尾ノ背寺跡が営まれる. このころ,坂出市櫃石島・がんど遺跡(寺院.墓地出土)が営まれる. このころ,善通寺市・中村遺跡(掘立柱建物,溝,土〔コウ〕(#「コウ」は文字番号なし)出土)が営まれる. このころ,善通寺市・上一坊遺跡(石組み井戸,溝―N―30°―W,ピット中, もしくはピット中の小皿上から北宋銭出土)石積墳墓が普及する(豊浜町大木塚― くちはげ白磁出土) このころ,高松市・高松城東ノ丸跡下層墳墓群が営まれる. 16世紀 このころ,坂出市・下川津遺跡の中世屋敷跡が営まれる.