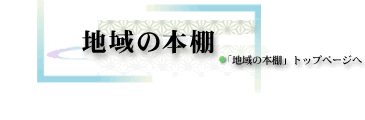
入力に使用した資料
底本の書名 讃岐ものしり事典(p178~180)
底本の編者 香川県図書館協会
底本の発行者 香川県図書館協会
底本の発行日 昭和57年4月1日
入力者名 坂東直子
校正者名 磯崎洋子
入力に関する注記
文字コードにない文字は『大漢和辞典』(諸橋轍次著 大修館書店刊)の
文字番号を付した。
JISコード第1・2水準にない旧字は新字におきかえて(#「□」は旧字)
と表記した。
登録日 2003年3月20日
-医学- 問 高松藩にあった医学校(「医学校」は太字)について(香) 答 明治2年、高松藩は柏原謙益を医学館開設取り調べ御用掛に命じ、4月26日に医学寮が創立 され、3年11月20日には仮医学所を中野天満宮境内鶴林寺においたが、翌4年には廃藩により 費用支出が困難になり廃止した。しかし、医師が戸長の尽力で病院が治療のかたわら医学生の 養成にあたり、明治6年7月17日には柏原謙益が官許を得て「明七義塾」を開いて医生を教え、 「明七雑誌」を出した-これが医事衛生雑誌の最初。 ○ 高松医学医事史(新修 高松市史 2巻別刷) 日本赤十字社香川支部病院々誌 P1 新修高松市史(Ⅱ) P710~ 問 柏原学而(「柏原学而」は太字)について(香) 答 医師謙好の三男として天保6年4月5日潟元村(今の高松市屋島西町)に生まれる。長じて 大坂緒方洪庵の門に入り蘭学、医学を学ぶ。のち一橋家に召しかゝえられ、将軍慶喜公の侍医 となる。幕末風雲急ななかにも、終始慶喜公について行動を共にした。明治時代になってから は静岡で開業し県立病院長も兼ねた。趣味として和歌をつくった。古武士の風格ある名医とし て慕われた。 明治43年11月5日、76歳で死去した。 ○ 新修高松市史2 P756 香川県医師会誌第11巻第2号 P38 -179- 問 千金丹(「千金丹」は太字)について(香) 答 讃岐千金丹の故事来歴は不詳のようであるが、明治18年頃より売出され、大正年間より昭和 の初期における讃岐売薬の全盛期には、有力な地場産業の一つであり、富山・滋賀に次いでい た。 この讃岐売薬の表看板が千金丹であり、最盛時には県下に大小300の製造業者があったと いわれているが、今日では昔日の面影はない。 千金丹は一種の清涼剤ともいわれ、また、解毒剤ともいわれており、明治13年頃に独特の千金 丹売りにより全国に知られるようになったが、利益莫大のため模倣者が続出し、実の本家はわか らないようである。寺田寅彦の随筆「物売りの声」や荒井とみ三の「讃岐民俗図誌」第6巻には、 讃岐千金丹の呼び声と薬売りの服装がでている。 ○ 香川県文化財調査報告9 明治100年にちなむ高松今昔記1 讃岐民俗図誌6 看板考8 物売り行商篇 讃岐郷土画集1 物売り今昔 P8 讃岐公論 昭42年5月号 明治100年春告げ鳥の千金丹(四国新聞)昭和41.4.12 岩波文庫 寺田寅吉(#「吉」は底本のママ)随筆集5 P86 問 高松藩の薬園(「高松藩の薬園」は太字)について(香) 答 五代藩主頼恭は宝暦9、10(1759~1760)に栗林荘内に薬園をもうけ、採薬係りのものをし て、国内各地から薬草を採集し、それらの薬草を栽培した。 この栗林薬園は当時は梅木原薬園と称していた。頼恭の当時は、薬草採取班として、初め平賀 源内後に池田玄丈、深見作兵衛が頭取となり他小姓5、6人で南は安原の奥、東は阿波境、西は 金比羅山を限りに一週間くらい泊りがけで出張して採取した薬草を薬園に送って植えつけた。 宝暦9~10年頃の薬園の広さは、約3段歩とある。次に製法した薬種は山茱萸、山査子、〔ヨ ク〕苡仁(#「ヨク」は文字番号32106)、生地黄、当帰、紫蘇、〔カク〕香(#「カク」は 文字番号32406)、〔ケイ〕芥(#「ケイ」は文字番号30940)、莪求、鬱金、決明子らである 。また芍薬、知母、黄〔キン〕(#「キン」は文字番号30724)、鳥薬は3、5年に1度ずつ 薬種に仕立てられた品である。この15種のほかに製法された薬種は見腫消、埋〔カク〕香(# 「カク」は文字番号32406)、馬蹄決明、胡〔ダ〕(#「ダ」は文字番号31009)、玄参、威霊 仙、沙参、百部根、王不留行、良姜、天門冬、藁本、鳥頭、川〔キュウ〕(#「キュウ」は文 字番号30678)、木通、菊花、通脱木、唐大黄モミジハグマ等である。 これ等の薬種の薬効面は、強壮剤を筆頭に感冒解熱、鎮痛、消化、利尿といった、すなわち常 備薬に属するものが多い。池田文泰が薬種に仕立てたものを文化3年(1806)より同6年(1809) にわたって民間の薬種問屋に払い下げをした薬種の種類は山査子、上紫蘇、中紫蘇、莪求、細 莪求、晒桑白皮、皮付桑白皮、山茱萸、百部根、当帰、知母、大鬱金であった。讃岐にはおお よそ300余種の薬用植物がある。 -180- ここで主な薬種と効用をあげてみよう。 ・〔ヨク〕苡仁(#「ヨク」は文字番号32106)(ハトムギ)……消炎、鎮痛、化膿症、関頭痛、 ・紫蘇(ジソ)……十二指腸虫駆除薬、腸内異常発酵制止 ・当帰(トウキ)……浄血、鎮痛、強壮薬、貧血症 ・決明子(エビスグサ)……便秘症 ・鳥頭(ヤマトリカブト)……鎮痛、冷症、関節痛、下痢、腹痛 ・鬱金(ウコン)……黄疸、胆石症、膵臓炎 ・知母(ハナスゲ)……解熱、利尿、鎮静薬 ・黄〔キン〕(#「キン」は文字番号30724)(コガネバナ)……解熱、喀血、鼻血らの血止 ・鳥薬(テンダイウヤク)……鎮痙 ・山茱萸(サンシュ)……強壮、強精薬 ・生地黄(カイケイジオウ)……補血、強壮剤、貧血、喀血 ・芍薬(シャクヤク)……鎮痙、止痛、胃けいれん、腹痛、神経痛、月経痛 ○ 讃岐薬用植物 日本薬園史の研究 P289~ 薬用植物画譜 香川の薬用植物 問 香川県下にある薬用植物(「薬用植物」は太字)について(香) 答 アカネ-通経、浄血、解熱、強壮。アケビ-利尿。アサガオ-峻下剤。アロエ(イシャイラ ズ)-緩下剤、通経、火傷、創傷。イタドリ-通経、利尿、緩下。イチヤクソウ-利尿、脚気。 イノコヅチ-収剣、利尿。ウツボグサ-利尿、子宮病。ウド-風邪、淫腫、中風。エビスグサ -緩下、強壮。オオツヅラブジ-利尿、神経痛、リウマチ。オオバコ-利尿、健胃。 オウレン-健胃。オモト-強心、利尿。カワラヨモギ-黄疸。カンアオイ-頭痛、発汗、 〔キョ〕痰(#「キョ」は文字番号34220)。キキョウ-〔キョ〕痰(#「キョ」は文字番号 34220)。キハダ-健胃。キンミヅヒキ-収剣、強壮、下痢止。クコ-解熱、強壮。 クズ-発汗、解熱。ゲンノショウコ-整腸。ザクロ-駆虫剤。サルトリイバラ-発汗、毒下し、 通風。サンショウ-健胃。サフラン-婦人病、鎮痛、頭痛、感冒。シソ-健胃、利尿。シャクヤ ク-鎮経、利尿、婦人病。ショウガ-健胃。ショウブ-健胃、浴場料。ジュズダマ-利尿、健胃。 センダン-蛔虫、條虫。センブリ-健胃。ダイコンソウ-強壮、解熱、利尿。ツリガネニンジン -〔キョ〕痰(#「キョ」は文字番号34220)、健胃、強壮。ドクダミ-化膿、腫物、創傷、利 尿。トリカブト-リウマチ、神経痛。ナンテン-百日咳、喘息。ニンニク-強壮、加工食品原料。 ノイバラ-峻下剤、利尿。ハシリドコロ-鎮痙、鎮痛。 ヒガンバナ-吐剤、〔キョ〕痰(#「 キョ」は文字番号34220)。ホオノキ-健胃、リウマチ。ボタン-婦人病。ミシマサイコ-解熱。 ヤマゴボウ-利尿。ヤマノイモ-強壮、夜尿。ユキノシタ-諸瘡、凍傷、毒虫の刺傷、解熱。 リンドウ-健胃。ワレモコウ-収剣、止血。 ○ 香川の薬用植物 讃岐薬用植物実験的療法 香川県地方の薬用植物 -181- 郷土薬用植物標本目録 香川県の薬草略史-月刊香川 昭和37.8